はじめに
2008年は,気候変動の要因となる温室効果ガスの削減に向けた京都議定書の約束期間の開始年に当たる。2008~2012年の5年間に先進国全体の温室効果ガス排出量を1990年と比べ5%削減するために,国際社会の温暖化防止の取り組みが本格化する。また今年は,2013年以降の地球温暖化対策を協議する洞爺湖サミットも予定されており,自動車も含めた環境対策がグローバルに動き出す年とも言えよう。
これらの社会的要請に沿ってエンジン油の規格も変化しつつある。本稿では,エンジン油規格の最近の動向につき概説する。
1. ガソリンエンジン油の動向
ガソリンエンジン油の性能分類としては,日米の自動車メーカーで組織されるILSACが制定する規格が最も市場ニーズを先取りしたエンジン油規格として認知されている。現在は2004年に制定されたILSAC
GF-4規格が最新であるが,2010年には次世代のGF-5規格が制定される予定で,現在規格および試験法の開発が鋭意進められているところである*1。
ILSAC GF-5は,GF-4と比べて,以下の3つの項目で性能を強化することが合意されている。
a)省燃費性能とその持続性の強化
b)エンジンを保護する性能の強化
c)排気浄化装置を保護する性能の強化
a)については,現在開発中のSequence VID試験で,新油の省燃費性能のみならず,オイル交換距離に至るまで省燃費性能を維持する性能がGF-4よりも高いレベルで要求されることになる。
b)については,エンジンの高出力密度化,高回転化およびオイル交換距離の延長などにより,エンジン油の使用環境が年々苛酷となっている実情に対応するものである。
例えば,ピストンリング周辺のデポジット生成を抑制し,オイル消費を低減することにより排気触媒の被毒劣化を防ぐ性能や,ゴムシールへの適合性もより高度に求められる。また,可変バルブ機構,シリンダ休止機構などの採用により,エンジン油のエアレーション(泡巻き込み性)が問題となること,直噴式エンジンの増加により,エンジン油へのスス混入が増加し,摩耗が問題となる場合があること,バイオガソリンなど従来のガソリンとは異なる基材が燃料として用いられることへの対応(乳化性や防錆性など)が盛り込まれる予定である。
c)については,ますます厳しくなる排出ガス規制に対応して,排気触媒やO2センサーの活性低下を防止するため,エンジン油の基油や添加剤に由来する硫黄分,リン分などの濃度を細かく規定することが予定されている。
本稿執筆時点でのILSAC GF-5規格原案を表1に示す。ただし,詳細については現在関連業界間で協議中であり,規格内容が確定する2009年秋までには,多くの変更が加えられるものと思われる。特に,規格の対象となる粘度グレードについては,従来含まれていた10W-30を除外し,0W-20,0W-30,5W-20および5W-30の4グレードのみを規定することが提案されている。
|
表1 ILSAC GF-5規格原案(2007年2月案)
|
ILSAC GF-5の発効時期は2010年秋が予定されているが,検討が開始された2005年からの検討プロセスを表2に示す。2008年は,新しく導入されるエンジン試験の試験精度確認のためのマトリックス試験の実施と,その結果にもとづく試験法の制定が作業の中心となろう。
|
表2 ILSAC GF-5規格の制定スケジュール
* ILSAC / OIL:ILSACと石油・添加剤業界による合同会議体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお,ILSAC GF-5の市場導入と同時期にGF-5から粘度グレードと省燃費性の要求を抜いたAPI SNグレードが新たに設定されることとなろう。
一方,欧州では,ACEA規格の次の改訂が2008年10月に予定されており,各カテゴリーの見直し作業が開始されている。表3に本稿執筆時点での乗用車用エンジン油規格(A/BおよびCカテゴリー)の改訂案を示すが,欧州の場合ディーゼル乗用車の比率が高いことから,いずれもガソリン・ディーゼル兼用の規格となっているのが特徴である。今回の見直しは一部試験法の更新や規格値の若干の変更が中心で,2007年版と比較して大きな変化はない。
|
表3 ACEAエンジン油規格2008年版の原案(乗用車)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次に,エンジン油の粘度特性を分類するSAE粘度分類(SAE J300)も見直しが進められており,2007年11月に最新の改訂版が発行された。エンジン油の粘度分類に関してはここ数年,(1)省燃費エンジン油の分類・定義の導入,(2)低温粘度の規格値の見直し,とりわけCCS粘度の規格からの除外,(3)高温高せん断粘度の規格値見直し,などが検討されてきたが,今回の改訂では(3)のみが採用になり,(1)と(2)は継続検討となった。
今回の改訂点は,SAE 40のうち0W-40,5W-40,10W-40の高温高せん断粘度の規格値を,従来は2.9mPa・s以上であったものが,3.5mPa・s以上に変更された点のみで,15W-40,20W-40,25W-40,シングルグレード40番の高温高せん断粘度は,従来どおりの3.7mPa・s以上で変更ない。この変更は,40番のエンジン油がディーゼルエンジンに多用されることを配慮したものであるが,モーターサイクル用4サイクルエンジン油の規格であるJASO
T 903では粘度番手に関係なく高温高せん断粘度を2.9mPa・s以上と規定しているため,例えば10W-40油の粘度特性がモーターサイクルの要求に合わなくなることが懸念されている。
なお,JASO T 903の動きとしては,現在ギヤピッチング評価法の開発およびクラッチ摩擦特性評価試験方法(JASO T 904)のクラッチフェーシング材の変更検討が進められており,2010年の規格改正に反映される予定である。
一方,モーターサイクル用2サイクルエンジン油の規格であるJASO M 345については,排出ガス対策の困難さから2サイクルエンジンの製造が衰退傾向にあり,現行規格を見直す動きは今のところない。
2. ディーゼルエンジン油の動向
ディーゼルエンジン油の分野では,米国のAPIサービス分類が国際的に普及しているが,最新のグレードであるAPI CJ-4が2006年10月に制定されてから間もないので,次世代規格であるPC-11の開発は今のところ着手されていない。しかしながら,EMA(米国エンジン製造者協会)ではCJ-4オイルでの市場不具合の発生状況調査や,バイオディーゼル燃料を用いた場合の潤滑油およびエンジン耐久性に及ぼす影響の調査を開始している。現在EMAでは以下の3種類のエンジンを用いてB20バイオディーゼルによる耐久試験を実施する計画である。
- キャタピラー C13エンジン
- カミンズ ISMエンジン
- マック T12エンジン
試験後のエンジンの詳細な検査と,エンジン油の分析によってバイオディーゼル燃料使用時の問題点を明確にする。
このような背景のもと,次世代のディーゼルエンジン油規格は次のような要求性能の構成になると考えられている。
- バイオディーゼル燃料への適合性
- API SLレベルの酸化安定性
- ターボチャージャーデポジットの抑制
- 省燃費性
- 排気対策装置への適合性
- その他の性能についてはCJ-4と同等
PC-11の開発が本格化するのは2008年後半からと思われ,2012年頃の市場導入が予想される。
一方,欧州のヘビーデューティーディーゼルエンジン油規格はACEAのEカテゴリーであるが,上述したように2008年10月を目途に規格の見直しが検討されている。本稿執筆時点での規格案を表4に示す。今回の改訂では,E2カテゴリーが廃止となり,新たにユーロ5排気対策エンジン用の高性能エンジン油としてE9カテゴリーが登場する見込みである。
|
表4 ACEAエンジン油規格2008年版の原案(ヘビーデューティー車)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本のディーゼルエンジン油規格は排出ガスの新長期規制に対応するJASO DH-2(ヘビーデューティー用)およびDL-1(ライトデューティー用)が2005年に制定されており,当面は改訂の必要がない。現在は,これらのJASO規格を,日本製のトラックが輸出されているアジア諸国にも普及させるための情宣活動に力を入れているところである。しかしながら近い将来には,より厳しい排出ガス規制が導入されることは確実であり,日本においても次世代のディーゼルエンジン油規格の検討を開始すべき時期にあると言えよう。
3. 省燃費オイルの動向
前述したように,地球温暖化防止の観点から自動車の省燃費化が求められている。米国では2007年12月にブッシュ大統領が,CAFE(企業平均燃費)基準を2020年までに現行の27.5マイル/ガロンから35マイル/ガロンに引き上げる法案に署名した。欧州ではACEAとEUの合意により,自動車のCO2排出量を1995年対比で2008年までに25%削減することが当面の目標となっている。さらにEU指令として1995年対比で35%のCO2排出削減を2012年までに達成することが提案されており,欧州の自動車メーカーは燃費向上技術に全力を傾注している。
日本では,1998年に設定された燃費規準でガソリン車の10.15モード燃費を1995年対比で2010年までに21.4%向上させることを義務付けていたが,新たに2007年に新燃費基準が制定され,2004年対比で2015年までに乗用車で23.5%,小型バスで7.2%,小型トラックで12.6%の省燃費を達成することが義務付けられた。また,大型車両についても2002年対比で平均12.2%の省燃費を2015年までに達成することを求める燃費基準が2006年に設定されている。これらの自動車の省燃費基準のうち,乗用車の基準を日米欧の比較でまとめたのが図1である。ただし,燃費の測定方法や,車両の平均排気量が異なるので,あくまでも参考とされたい。
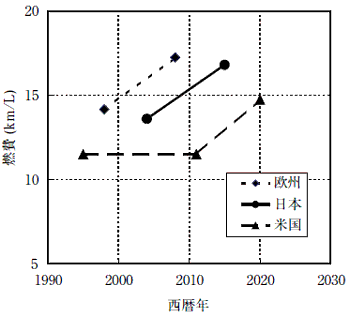
図1 日米欧の乗用車燃費基準の比較
自動車の省燃費を達成するためには,車体の軽量化,ハイブリッド化,エンジンや駆動系の効率向上などの対策があるが,エンジン油が燃費に影響を及ぼすことは古くから知られており,ILSAC規格に見られるように,近年のエンジン油規格には省燃費性能を規定するケースが増えている。
エンジン油による省燃費化の方策としては低粘度化とフリクションモディファイヤーの添加による摩擦低減の2つのアプローチがある。とりわけ低粘度化の効果は,シングルグレード油や高粘度のマルチグレード油(15W-40,20W-50など)が用いられているケースと比較すると顕著である。
図2は,アジアの各国におけるガソリンエンジン油の粘度グレードの使用実態調査結果を示すが*2,中国,フィリピンのようにシングルグレード油が主流の国が依然として存在することと,マルチグレード油が主流の国でも日本,韓国以外は高粘度油が中心であることがわかる。このようなエンジン油の使用実態に対して,中国および東南アジアの諸国で10W-30油の普及を促進することにより,国単位で3~5%の省燃費が達成できるとの試算もある*3。
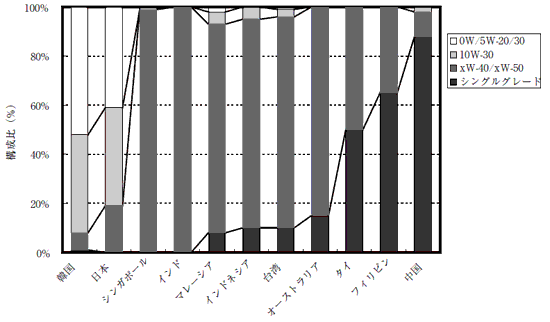
図2 アジア各国のエンジン油粘度グレード分布(ガソリンエンジン油)
このような背景から,SAE(米国自動車技術者協会)の下部組織であるSAE Steering Committee for Asiaでは,アジア地域への低粘度エンジン油(10W-30が目安)の普及を企図しており,3つのワーキンググループ(乗用車用エンジン油WG,モーターサイクル油WGおよびヘビーデューティーディーゼルエンジン油WG)がこれを推進している。
モーターサイクル油WGの活動の一環として,図3にモーターサイクルの燃費に及ぼすエンジン油粘度の影響を実測した例を示すが*4,20W-40油との対比で10W-30油は5~8%の省燃費をもたらしていることがわかる。
さらに2007年からは,SAE Asiaの低粘度油普及活動に,自動車技術会が賛同して省燃費エンジン油普及タスクフォースを結成し,共同でエンジン油の低粘度化の方策を検討している。
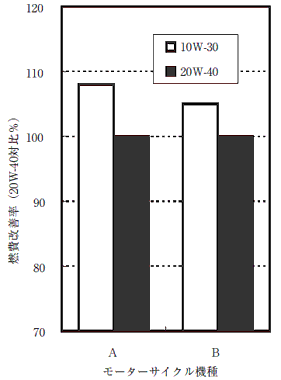
図3 エンジン油粘度と実車燃費の関係(ガソリンエンジン油)
おわりに
エンジン油規格の最近の動向につき概説したが,近年の技術開発は環境対応が主なドライビングフォースであることは論を待たない。我が国は環境対応技術において世界をリードする立場にあると言われているが,潤滑油の処方技術についても最先端の技術を有していると思われる。
今後は,日本の潤滑油技術をアジア地域のみならず,グローバルに展開することにより地球環境問題の解決に向けて貢献していくことが望まれる。
<参考文献>
*1 浜口 仁:自動車用エンジンオイル規格の動向,月刊トライボロジー,No.242(2007)
*2 H. Hamaguchi:SAE Steering Committee for Asia資料,(2006)
*3 浜口 仁:自動車技術会次世代燃料潤滑油委員会資料,(2007)
*4 M. Akagi:SAE Steering Committee for Asia 資料,(2007)



