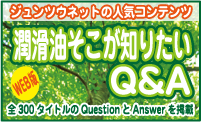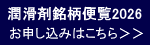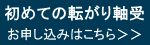保全業務を分社化して協力会社に任せたらよいのではないかと言われています。今まで自分なりにきちんと設備を管理してきたつもりです。この状態を維持しながら協力会社に委ねる方法がありますか。
解説します。
どんなことでも同じですが,分社化にも良い点と悪い点があります。
両者を冷静に検討して会社として有利になる方向に進むことになるでしょう。しかし,この場合,弱点を残したままにせず,改善して総合的に効果が増加するように進めるべきです。
ここでは分社化の良い点と悪い点をあげておきます。
1.良い点
(1)製造工場では主として製品を生産することで利益を挙げます。したがって,製品の量と質で,作業員の評価が決まります。生産に直接かかわっている作業員は仕事そのもので直接評価されます。一方でメンテナンス担当者は設備を安定さ,製品の量と質を保証する場を提供することになり,直接生産にタッチするわけではありません。仕事の完成度と生産量は必ずしも一致しません。
したがって,自分たちの仕事の良さで直接評価されることにはなりません。この辺がメンテナンス担当者のモラルに影響してくると思います。分社化するとメンテナンス専門会社になりますので,仕事そのものが直接,評価の対象となりますのでモラルがあがってきます。
優れた作業員(メンテナンス)は直接企業(メンテナンス会社)の業績に自らの力を発揮できることになります。
(2)上下ともにメンテナンス専門家ですので,育成,情報交換,相談,目標設定,検討会議などすべてメンテナンスが主体となります。
(3)メンテナンス技術が企業として蓄積される。
(4)メンテナンス専門企業として多くの工場を担当することになると経験が増えて,技術・技能が磨かれる。
(5)関連工場の高年齢作業者を設備に詳しい作業者として受け入れることができる。定年後の雇用の受け皿ともなる。
(6)作業仕様をはっきりさせて,きちんとした請負作業になると,能率が上がり依頼者,作業者ともに利益が出る。
(7)能率を上げて余った時間で親会社以外の工場のメンテナンスを担当することができる。
2.悪い点
(1)自社にメンテナンス技術・技能がなくなる。
(2)分社化当時は親会社の生産に興味を持っているが,そのうち忘れて,メンテナンスが事務的になる(頼まれたことしかやらなくなる)。生産会社からすると自由が利かなくなる。
(3)自由を効かせるために丸抱えで雇うと,以前より費用がかかることがある。
(4)契約方法簡素化のために時間契約になる恐れがある。この場合,一生懸命に働いても,もらう金が同じになり,能率を上げなくなる。勉強もしなくなる。
(5)親会社との契約で余った時間が有効に使えないとメンテナンス専門会社として成り立たない。
(6)親会社の名前で優秀な人材を確保することができていた場合,独立してメンテナンス専門会社となると,優秀な人材を確保できなくなる恐れがある。
(7)分社化された企業は教育などを管理費として自分たちの費用で実施しなければならないので,親会社との契約が難しくなる(見かけの労務費で仕事を契約すると余分な費用の捻出ができなくなる)。分社化された企業は,技術力向上が停止し,安かろう悪かろうの企業となり,親会社は総合的に技術力が劣ってくる。
コンディションモニタリングBOX
メーカー別製品一覧
コンディションモニタリング機器の紹介
解説 コンディションモニタリング
- 設備診断技術の動向と今後の展望
大阪市立大学 大学院 川合 忠雄 - ガスタービンにおける設備診断の現状と課題
IHI 小林 英夫 - 原子力発電プラントにおける設備診断の現状と課題
東芝 渡部 幸夫 - 鉄鋼プラントにおける設備診断の現状と課題
新日本製鐵 村山 恒実 - 化学プラントにおける回転機設備診断機器の有効な活用法
三井化学 三笘 哲郎 - 化学プラントにおける設備診断の現状と課題
昭和エンジニアリング 里永 憲昭,梶原 生一,山路 信之,三重大学 陳山 鵬 - 地震時のエレベーター自動診断・自動復旧システムの開発
三菱電機ビルテクノサービス 西山 秀樹 - 設備診断技術を設備管理にどう活かすか
新日本製鐵 藤井 彰 - 振動診断のメカニズムと特徴,今後の展望
三重大学 大学院 陳山 鵬 - AE診断法とその特徴,今後の展望
THK 吉岡 武雄 - 超音波診断のメカニズムと特徴,今後の展望
高知工科大学 竹内 彰敏 - 音響診断のメカニズムと特徴,今後の展望
広島大学 大学院 中川 紀壽 - 潤滑油測定のメカニズムと特徴,今後の展望
福井大学 大学院 岩井 善郎