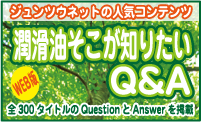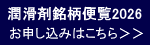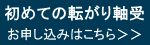設備管理の目標は設備効率を最大にすることであるといわれます。すなわち
設備効率=設備の生み出すアウトプット/設備に対するインプット
の式で分かるように,インプットが一定であればアウトプットを最大にすれば設備効率も最大になります。このアウトプット最大の要は(1)設備の故障(回数)を減らす(信頼性の向上)ことと,(2)故障による休止時間を最小にする(保全性の向上)こと であるといわれますが,この二つはあまり変わらずすべて(1)の信頼性向上に含まれると思いますが,なぜこのように分けて考えるのか教えてください。
解説します。
信頼性と保全性について
簡単に見れば同じ事のように見えます。さらにひとつの対策で,結果が同じになることがあります。しかし,設備を新設するとき,改造するときはこの一つ一つが生かされて,詳細に検討しなければなりません。
改造の場合など問題点が目の前にあるとそのことにだけにこだわり,全体を見つめず,結果的には生産阻害に陥ることがあります。今から実施する改造が信頼性向上なのか,保全性向上なのかをしっかり把握し,もう一方の目的からすると結果的にどのようになるかを検証しておく必要があります。一般に現場で刹那的実施される改造は違うトラブル発生を引き起こす可能性があります。
両者の考え方を理解してもらうために事例を紹介します。
1. 発信器を取り巻く配管
図1は,フランジ継手を十分に使い,漏れなど事故のときに簡単に解体してまし締めを可能にしたり,配管変更を容易にしたりするものです。いわゆる保全性に重点を置いたものです。
しかし,結果的には取り外ししやすいことは,一方でゆるみやすい,外れやすいことになり漏れという事故が発生する可能性が高い信頼性の低いものとも考えられます。
|
図1 継手を十分使った配管事例 |
図2は,継手が少ない配管の事例です。もしバイパスのストップバルブのねじ込み部から漏れが発生したらまし締めは不可能で配管を切断して修理せねばなりません。いわゆる地獄といわれる配管方式です。しかし,ねじ部がほとんどないということから漏れのチャンスが少なく信頼性重視の配管です。
|
図2 継手を最小限に抑えた配管の事例 |
このケースではどちらを選ぶか生産方式,環境によりますが,両者の欠点を補い改造を加えて,信頼性が高く,しかも保全性をあまりそこなわない方式を採用することをお勧めします。
2. 大型構造物の摩耗部分
大型の構造物主要部に大型治具を取り付けて精密な作業を実施しているもが多くあります。この場合,構造物側に部分的な摩耗が発生することを恐れて,図3(a)のように,治具側に少し柔らかめのライナーを取り付けて,治具側で摩耗対策を施してあるのが一般的です。これもひとつの保全性を考えた対策です。
|
図3 ハウジング面をライナータイプに変更した事例 |
しかし,この状態が長く続くとハウジングがライナーに叩かれて面荒れを起こしたり,部分的に摩耗したりすることがあります。したがってこのままではライナーが変形して役に立たなくなります。
そこで最近の技術では,優れた溶接肉盛と現地加工の技術により比較的短時間でライナー取り付け部分を加工し,ハウジング自体をライナー方式に改造することも可能です。
ここで注意することは頻繁に取り替えなければならない治具(刃物,ロール,ポンチなど)についてです。この事例では大きな一体ものとして治具を取り替えております。実際に消耗しているところはこの中の,ロールであったり,ポンチであったり,刃先であったりします。そのために現地で分解して新しい消耗品を入れ替えている現場を見ることがあります。これは大変な間違えです。せっかくワンタッチで交換できるようにオフラインで消耗品をセットして,一体予備できる構造になっているわけですので,必ず予備もコンプリートで整備しておいてください。最大の保全性向上です。
3. 保全性より信頼性を重視した事例
図4にラインシャフト方式のローラーテーブルを示します。ローラーが摩耗したり,ベアリングの損傷があったりした場合,簡単に一本だけ取り替えるような構造ではありません。無理に部分的に交換している現場もありますが,取り替え後はアンバランスとなり,取り替え効果が発揮されません。
|
図4 ラインシャフト方式のローラーテーブル |
このような設備では予備として一式をそろえ,オフラインで歯当たりまでチェックして,全体を一度に取り替えてしまうことをお勧めします。一個所だけのギヤ損傷などの場合はその場で歯車だけを外しアイドルローラーとして一時しのぎをすることも可能です。
ローラーやギヤを取り替えるときは必ず一式で交換し,信頼性の高い設備として運転してください。
4. 保全性を優先して失敗した事例
目先のトラブル解決のことだけにとらわれて,信頼性の検討を忘れてしまった事例です。
ラックギヤが良く破損しました。大型なので取り替えも大変でした,もちろん費用もかかります。そこで図5に示すような改善が提案され,直ちに実施されました。ギヤの部分だけを現地で取り替えるというものです。
|
図5 ラック部を安易に改造した事例 |
しかし,その結果は歯とりつけ部分の根元が折れてしまい大きな事故となりました。冷静に判断すればすぐ分かることでしたが,担当者は歯の取り替えやすさのみに眼が言っていたようです。保全性向上を目的とした場合は特に強度,全体としてのバランスに注意してください。
コンディションモニタリングBOX
メーカー別製品一覧
コンディションモニタリング機器の紹介
解説 コンディションモニタリング
- 設備診断技術の動向と今後の展望
大阪市立大学 大学院 川合 忠雄 - ガスタービンにおける設備診断の現状と課題
IHI 小林 英夫 - 原子力発電プラントにおける設備診断の現状と課題
東芝 渡部 幸夫 - 鉄鋼プラントにおける設備診断の現状と課題
新日本製鐵 村山 恒実 - 化学プラントにおける回転機設備診断機器の有効な活用法
三井化学 三笘 哲郎 - 化学プラントにおける設備診断の現状と課題
昭和エンジニアリング 里永 憲昭,梶原 生一,山路 信之,三重大学 陳山 鵬 - 地震時のエレベーター自動診断・自動復旧システムの開発
三菱電機ビルテクノサービス 西山 秀樹 - 設備診断技術を設備管理にどう活かすか
新日本製鐵 藤井 彰 - 振動診断のメカニズムと特徴,今後の展望
三重大学 大学院 陳山 鵬 - AE診断法とその特徴,今後の展望
THK 吉岡 武雄 - 超音波診断のメカニズムと特徴,今後の展望
高知工科大学 竹内 彰敏 - 音響診断のメカニズムと特徴,今後の展望
広島大学 大学院 中川 紀壽 - 潤滑油測定のメカニズムと特徴,今後の展望
福井大学 大学院 岩井 善郎